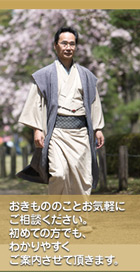織絵屋のブログ
01/30: 店主のよもやま話⑤
織絵屋の松山です。今年は盛岡地区では元旦も雪でしたが、2日は良い天気で、キレイな日の出を拝むことが出来ました。今月も共に元気に明るくがんばっていきましょう!

1月2日の日の出
隣家と我が家を結ぶ雪の回廊?
燐家の奥さんが、冬になると日が当たらないので我家の庭に洗濯物を干しに来ます。でも、屋根から落ちる雪が通路を塞ぐと我家の庭まで来られなくなります。気の毒に思ったので、数年前から雪が降る度にしっかり雪かきをして通路を確保するようにし、○○回廊と呼んでいます。

朝日を浴びる雪の回廊
遠くの親戚より隣人です。いつまでも仲良くしたいものです。
今月の24節気 「土用」 「立春」 「雨水」
1月17日~2月2日までは冬の土用です。心身ともに不調になりやすい頃ですので、無理をせずにゆっくり過ごしましょう。
2月3日が節分です。良い一年になるように豆まきで厄を祓い、福を伸び込みましょう。
2月4日、立春(りっしゅん)に入ります。24節気の一番目で、一年の始まり、春の始まりです。
冬至と立春を比べると、日の出は9分早いだけですが、日の入りは44分も遅くなって、昼の時間が53分も長くなるんですね。
立春の朝、『立春大吉』と書かれた半紙を玄関などに貼ると魔除け、招福になると言われています。
我家でも玄関に毎年貼っています。ご利益はどうか分かりませんが、気持ちが清々し
くなります。

我家の玄関
『立春大吉』の半紙を欲しい方は、店に用意していますので、気軽に「立春大吉の半紙をください」とお申し出ください。
19日、雨水(うすい)に入ります。降っていた雪も雨に変わり、積もった雪や氷も解け始める頃です。
農作業を始める目安ともされ、大地が雪解け水で潤い、草木が芽吹き始め、春の訪れを感じる頃です。
雨水に雛人形を飾ると良縁に恵まれると良まれますが、これは、ひな祭りが元々、人形(ひとがた)災厄を移して川に流す行事がルーツだったことに由来します。

ちなみに、24節気はユネスコの無形文化遺産に登録されています。
桜のメッセージカードで気持ちを明るく!
今年も『絆の一本桜』を作りたい!
元々は東日本大震災の鎮魂のために始めた桜のメッセージカードを貼って製作しました。
新聞やNHKなどから幾度も取材報道してもらいましたが、今年も作りたいと思います。

店頭に桜のメッセージカードを用意していますので、ご来店の際、「元気に明るくなるメッセージ」を記入して、ご協力ください。
きものを着る気軽なイベント前半予定
2月11日…おやつの会(店内)
3月14日…美術館「レオレオニ―」展を鑑賞
4月…きものツアー(角館)
5月…おやつの会(店内)
6月…きものツアー
・「おやつの会」はお菓子を取り寄せ、1,000円の参加費で着物を着て一緒に楽しむイベント
※あなたのおすすめのお菓子があれば教えてください。
・きものツアーの行き先は角館以外未定
※車で、1時間半ほどで行きたい場所、また、都合の良い曜日があればお知らせください!
ぜひ、お友達をお誘いください。
今号も読んで下さり、ありがとうございます。
令和8年1月22日
01/30: 絹素材の「きもの」の魅力について
織絵屋の松山です。今回、「きもの」の素材としての絹の魅力についてのべます。
絹は三千年以上前に、中国で生まれ、シルクロードを渡りヨーロッパにも伝わり、それまで麻とウールしか知らなかった人々はその光沢やつや、柔らかい風合いに驚き、絹を金と同じ重さ買い求めたそうです。
絹は蚕から作られますが、「蚕」は天から人間が授かった宝物です。繭から採れる糸は1200mにもなります。一枚のきものにはおよそ2,600個の繭が必要です。とても細くて超長い繊維だから、あの絹の独特のツヤや光沢、柔らかな肌触りが生まれるのです。

ほぼ、毎日着物を着る私が感じていることですが、木綿や麻は丈夫でお手入れが簡単なので使い勝手は抜群です。でも、着た時にテンションが上がることはありません。
しかし、絹素材のきものは、ちりめんでも、お召でも、紬でもそうですが、袖を通した瞬間にテンションが上がります。体も心も喜ぶ感じがします。
絹はデリケートなので、扱いには気を使いますが、吸湿性、放湿性に優れ、また静電気も起きにくく、さらに紫外線をカットしてくれます。
「きもの」はそんな最高の素材に、工芸的な染めや織りを施しているから体も心も喜び、着る人を元気にしてくれるのだと思います。
12/27: 店主のよもやま話④
織絵屋の松山です。令和8年、明けましておめでとうございます。本年も、元気に明るく共にがんばっていきましょう!
上野動物園のパンダ舎でガードマンのアルバイト
上野動物園のパンダが今月下旬に返還されるようです。上野動物園に別れを惜しむパンダファンがたくさん訪れているニュースを見て、52年前を思い出しました。

実は私、パンダのカンカンとランランが昭和47年10月に、初来日した翌々年の4月と5月、日曜日と祭日だけでしたがパンダ舎の前でガードマンのアルバイトをしていました。
当時はすごい人出で、入場制限しながら事故が起きないように、ひたすら「立ち止まらないで下さい!」「立ち止まらないで下さい!」と声をかけ続け、人々を移動させる仕事でした。
パンダは寝ている時間が多くて、ほとんどの方は寝姿しか見られないので、少しかわいそうでしたが、私は目の前で元気に遊ぶパンダの姿を見られたのでラッキーでした。
今月の24節気 「小寒」 「大寒」
1月5日、小寒(しょうかん)に入ります。寒さが加わるという意味で、寒の入りです。この日から節分(2/3))までを「寒の内」といいます。
小寒の期間に、七草粥を食べる風習があります。節句・人日(じんじつ)の1月7日に七草粥を食べ、お正月の飲食で弱った胃腸を休ませる意味があるようです。
小寒から9日目を「寒九」といい、この日に雨や雪が降ると、その年は豊作になると言われています。
20日、大寒(だいかん)に入ります。大寒は一年で一番寒い時期を指します。
でも、実はこの時期を過ぎると、自然は徐々に春に向かい始めます。大寒は寒さのピークを意味するだけでなく、春の訪れを予感させる、希望に満ちた意味も込められているのです。
一年で一番寒い大寒の時期には、剣道や空手などの武道では心身を鍛える「寒稽古」が行われます。

寒の時期に行う寒稽古
また、日本酒や味噌、しょう油などを雑菌が抑えられる大寒の時期に仕込む「寒仕込み」も行われます。
大寒の時期に生まれた卵は「大寒卵」と呼ばれ、食べると一年を健康に過ごせるそうです。
12/27: 幻の染と呼ばれる『竹かご染』
織絵屋の松山です。染色技法には様々な種類がありますが、今回は「竹かご染」について述べます。「竹かご染」は「かご絞り染」とも呼ばれています。
この技法は、格子状に編んだ四角のカゴに、白生地を詰めて染め、独特のぼかしや不規則な模様を生み出す伝統的な染色技法です。
まず、カゴに白生地をくしゃくしゃにして詰めるのですが、職人の指の感触だけで均等に詰めます。
次に、詰めた白生地の上からジョウロで染料をかけ、一気に染めず、徐々に染料を染み込ませていきます。

その後、生地を詰め直しながら染色を繰り返します。
すると、竹かごに当たる部分と当たらない部分で、色の抜け方が異なるので絶妙なムラ(グラデーション)が生まれます。同じ柄は2点とないのが特徴です。
さらに、染まった生地の上から別な色で25回も繰り返し染め、万華鏡のような柄になるモノもあります。
ただ、現在では「竹かご染」ができる職人は極めて少なく、めったに見られない幻の染と呼ばれています。
11/25: 使える「お召(おめし)」って、なあに?
織絵屋の松山です。今回は「お召」について述べます。
お召とは、糸を染めてから織り上げる「先染め」の着物です。緯糸に強い撚りをかけた糸を使うことで、コシが強く、シワになりにくいという特性があります。
「お召」という名称は、今、放映中のNHK大河ドラマ『べらぼう』にも登場している第11代将軍・徳川家斉がこの織物を好んで着用し、「御召料」とされたことに由来します。

当初は貴族や武士に愛用されていましたが、やがて庶民の間でも晴れ着として広まりました。
明治・大正時代には、お召は女性の憧れであり、矢絣のお召しに海老茶の袴を合せた女学生スタイルが大流行しました。

戦後、お召の人気にあやかった人絹お召やウールお召などが大量に生産され、お召は敬遠されるようになり、一気に衰退してしまいました。
しかし、現代でなって、お召は丈夫で着くずれしにくく、裾さばきが良いことから、おしゃれ着としても人気があり、近年、復活してきました。
お召は先染めの着物ですが、色柄によっては高い格を持ち、お茶席や結婚式でも着用できます。
単衣にしても、袷にしても着用でき、軽くて着心地が良く、シワにもならず、また格式や老若男女にもとらわれない等、とても使い勝手の良い着物です。